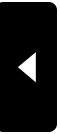宇佐山城址、壺笠山城址 ③
2023年12月24日
さて 次の目的地は 壺笠山城址です。
大津市穴太(あのう)地区の奥に三角に尖った小山が見えます。 比叡山に続く尾根の一峰に有るんです。
四ツ谷川添いを歩き始め、 古代の穴太野添古墳群の中を通り歩いて行くんです。
数十基もの古墳が残されていますが、多くは未整備のままですね…
更に林道を登り詰めて行きました。

深く切れ込み川面はかなり下ですが、 此の様な樹が生えていました。 前回も葉の有るときに
見掛けています。

今回は冬で 葉は有りませんでしたが、この様な実が付いていましたし・・・

此の様な冬芽も確認出来ました。
奇数羽状複葉の葉と共に ミカン科の キハダでは無いかと推察できました。

此れも少し離れた処のをズームしています。 キンポウゲ科の センニンソウですね~~~
既に果実が熟して 白い毛が拡がり 風に乗りいつでも遠くに飛ぶ準備が出来ていますね~
此の毛を 仙人の髭に見立てての仙人草の名前です。

林道から外れ 壺笠山の手前の急な山道を登り詰めると・・・ 尖った山頂ですが、意外と広い
城跡が有りました。

二つの看板が有りました。 一つは忠兵衛山。 今一つは 青山(あほやま)・389m。
此処も隣の 壺笠山と共に 朝倉方の城跡だそうです。
一度林道まで降り 隣の壺笠山城址へと登り返します。 昔の人はこの様に厳しい
山城を造り 走り回って戦をしていたのかと思うと感慨深いです。


広めの山頂部分は 木が茂り眺望は有りませんでしたが、この様な看板が有りました。
元々 古墳が有り、利用して城を作ったと書かれていますね~~~

此れが 縄張り図です。

壺笠山・421m でした。
勿論 戦では織田方の勝利で 浅井朝倉勢は撤退しています… その後小谷城攻めの戦で
壊滅されてしまうんですね( ^ω^)・・・
此処より更にもう一つ 奥の砦跡にも登ってきました。

此処は更に急な崖の上に有りました。 神輿山(見越山)・441mでしたね~~~
クリスマス・イブの今日は此処までです~~~ 登山と歴史但訪、更には植物等 自然観察も兼ねた
悠ちゃんの山旅でした。 明日にも此の続きが有るんです~~~
大津市穴太(あのう)地区の奥に三角に尖った小山が見えます。 比叡山に続く尾根の一峰に有るんです。
四ツ谷川添いを歩き始め、 古代の穴太野添古墳群の中を通り歩いて行くんです。
数十基もの古墳が残されていますが、多くは未整備のままですね…
更に林道を登り詰めて行きました。
深く切れ込み川面はかなり下ですが、 此の様な樹が生えていました。 前回も葉の有るときに
見掛けています。
今回は冬で 葉は有りませんでしたが、この様な実が付いていましたし・・・
此の様な冬芽も確認出来ました。
奇数羽状複葉の葉と共に ミカン科の キハダでは無いかと推察できました。
此れも少し離れた処のをズームしています。 キンポウゲ科の センニンソウですね~~~
既に果実が熟して 白い毛が拡がり 風に乗りいつでも遠くに飛ぶ準備が出来ていますね~
此の毛を 仙人の髭に見立てての仙人草の名前です。
林道から外れ 壺笠山の手前の急な山道を登り詰めると・・・ 尖った山頂ですが、意外と広い
城跡が有りました。
二つの看板が有りました。 一つは忠兵衛山。 今一つは 青山(あほやま)・389m。
此処も隣の 壺笠山と共に 朝倉方の城跡だそうです。
一度林道まで降り 隣の壺笠山城址へと登り返します。 昔の人はこの様に厳しい
山城を造り 走り回って戦をしていたのかと思うと感慨深いです。
広めの山頂部分は 木が茂り眺望は有りませんでしたが、この様な看板が有りました。
元々 古墳が有り、利用して城を作ったと書かれていますね~~~
此れが 縄張り図です。
壺笠山・421m でした。
勿論 戦では織田方の勝利で 浅井朝倉勢は撤退しています… その後小谷城攻めの戦で
壊滅されてしまうんですね( ^ω^)・・・
此処より更にもう一つ 奥の砦跡にも登ってきました。
此処は更に急な崖の上に有りました。 神輿山(見越山)・441mでしたね~~~
クリスマス・イブの今日は此処までです~~~ 登山と歴史但訪、更には植物等 自然観察も兼ねた
悠ちゃんの山旅でした。 明日にも此の続きが有るんです~~~

Posted by 悠ちゃん4 at 11:35│Comments(0)
│山行