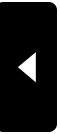医王山に向かう④
2023年05月22日
さて 奥医王山山頂での記念撮影も早々と終え、 今日の最重目標のお花を求めて
栃尾道へと下ります。

此処では今が盛りでしたね~ イワウメ科の イワカガミですね~~~

此のスミレは 葉裏は普通の緑でした。 コスミレとしましたが…
スミレは種類が多く正確ではないかも知れません。

栃尾尾根コースの入り口の分岐です。 此処から尾根を150m程下り、並行して登る沢コースで
ターンして来るのですが、・・・ かなりハードな様です。

カエデの仲間の様ですが 只今 捜索中です。


新緑が目に浸み込むようです。~ 此の辺りはブナが目立ちます。

葉の真ん中に見える黒紫色の班は、カバノキ科の ハシバミです。

カエデ科の ハウチワカエデなのですが、明るい日差しを浴び 緑が目に沁みる様でした。
子云う用途は違い、この時期の蒼いもみじの事を 青モミジと云いますね~~~
古来、日本では緑の事を青いと云いました。

所々に此の様な看板が有ります。 どんなラウンジ???

ブナ科の ブナの株立ちでラウンジと名付けているようです。 悠ちゃんも中に入ってみました~~~

此れはエルク広場と名が付く ブナです。

この時期 ユズリハも花を咲かせていました。

此方は キク科 コウヤボウキ属の クルマバハグマです。 コウヤボウキと同じ形の花を
沢山付けるんです。

アオイ科の カンアオイも未だ花は咲いていませんでしたが、綺麗な葉でしょう!


鈍痛を感じながら 漸く苦手な下りを居り切りました。 沢コースの登りへの分岐迄
辿り着きました。

ユキザサが此処では開花し始めていました。 沢山の株を見かけました。

シュロソウ科の エンレイソウです。

ツルアジサイは未だ蕾です。 花が咲けば イワガラミかも?

汗まみれ・・・足を引き摺りながらの歩きでしたが、この景色に出逢い! 疲れも忘れましたね~~~
念願の白山でした~~~
残雪を残す山の更に二つ奥に見える真白な山が 映っているんです。 好~く見ないと判らない?
今回も此処迄です~~~ 何とも多くの映像を撮ったもんですね~~~
栃尾道へと下ります。
此処では今が盛りでしたね~ イワウメ科の イワカガミですね~~~
此のスミレは 葉裏は普通の緑でした。 コスミレとしましたが…
スミレは種類が多く正確ではないかも知れません。
栃尾尾根コースの入り口の分岐です。 此処から尾根を150m程下り、並行して登る沢コースで
ターンして来るのですが、・・・ かなりハードな様です。
カエデの仲間の様ですが 只今 捜索中です。
新緑が目に浸み込むようです。~ 此の辺りはブナが目立ちます。
葉の真ん中に見える黒紫色の班は、カバノキ科の ハシバミです。
カエデ科の ハウチワカエデなのですが、明るい日差しを浴び 緑が目に沁みる様でした。
子云う用途は違い、この時期の蒼いもみじの事を 青モミジと云いますね~~~
古来、日本では緑の事を青いと云いました。
所々に此の様な看板が有ります。 どんなラウンジ???
ブナ科の ブナの株立ちでラウンジと名付けているようです。 悠ちゃんも中に入ってみました~~~
此れはエルク広場と名が付く ブナです。
この時期 ユズリハも花を咲かせていました。
此方は キク科 コウヤボウキ属の クルマバハグマです。 コウヤボウキと同じ形の花を
沢山付けるんです。
アオイ科の カンアオイも未だ花は咲いていませんでしたが、綺麗な葉でしょう!
鈍痛を感じながら 漸く苦手な下りを居り切りました。 沢コースの登りへの分岐迄
辿り着きました。
ユキザサが此処では開花し始めていました。 沢山の株を見かけました。
シュロソウ科の エンレイソウです。
ツルアジサイは未だ蕾です。 花が咲けば イワガラミかも?
汗まみれ・・・足を引き摺りながらの歩きでしたが、この景色に出逢い! 疲れも忘れましたね~~~
念願の白山でした~~~

残雪を残す山の更に二つ奥に見える真白な山が 映っているんです。 好~く見ないと判らない?
今回も此処迄です~~~ 何とも多くの映像を撮ったもんですね~~~

Posted by 悠ちゃん4 at 07:40│Comments(0)
│趣味登山会